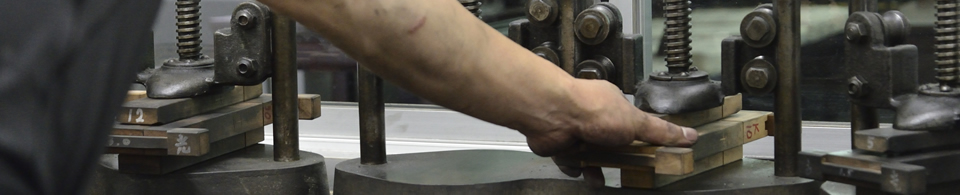墨のQ&A
膠使用の液体墨と合成糊剤使用液体墨の比較について。
ご質問にお答えする前に、なぜ合成糊剤使用の液体墨ができたのかをお話しします。
ご存じの通り昭和30年頃までは、液体墨と言えば墨汁しかありませんでした。これは膠と煤を練り合わせ、ニガリ(主成分 塩化マグネシウム)を大量に加え、液の比重を上げ、煤の沈殿を押さえると同時に塩漬けにすることにより膠のゲル化を防止し、さらにホルマリンで膠の腐敗を止めたものです。
この製品は和紙には向きませんが、吸い込みの少ない洋紙には黒光りして、絵の具の黒では出せない美しさを持ていましたので、非常に乾燥が遅いのですが良く売れていました。
反面、吸い込みの強い紙に書きますと皮膜を作る膠液が紙に吸いとられ、煤だけが表面に残り品の無い黒になり、おまけに乾燥が遅く、また、一度乾いても梅雨時分には空気中の水分を吸ってべたつく代物で、勿論表具のできるものではありません。
戦後10年近く経過し世の中も収まり、書道を志す人も増え始め、学校教育にも書写が取り入れられるようになりました。
この時期に先生方から墨汁に代わる乾きの早い、和紙に適した墨色の良い学童用の液体墨を造るようにとのご依頼を沢山戴くようになりました。
これからの学校教育には、授業時間の制約上良質な液体墨が必要になる。日本の書写教育のために早急に開発するようにとのことでした。
膠は固形墨を造るためには、これほど重要で便利な材料はありません。科学技術の進んだ現在でも膠に代わり得る材料は無いのです。膠の持つ特質に、温度が下がるとゲル化するという性質があります。煮魚の汁が、冬の寒い日にゼリ-状ににこごり、大変おいしいことは皆様もご存じのことと思います。
これは魚の膠質が気温の低下でゼリ-化したものです。
この性質を利用して冬に固形墨を造ります。膠は蛋白質ですので、細菌の寒天培養と同じく、気温の高い時期に製造しますと空気中の雑菌を拾い猛烈な勢いで繁殖し腐敗します。
墨が厳寒期に製造されるのは、腐敗菌の繁殖を抑えゲル化強度を高め、墨の内部から低温乾燥し墨を均一に締め上げていくのが墨造りで、墨がこの世に生まれてから2000年以上になりますが、この原理は変わりません。日本における墨の故郷奈良では、冬の風物詩になっております。

「宿墨は使うな」とお聞きになったことはあるかと思います。
また、日本画ではその都度、顔料を膠で練ってお使いになっているのをご存じかと思います。これには原因があるのです。
膠は固形墨の内部に取り込んで乾燥しますと100年単位の安定した状態を保ちますが、水中では加水分解により、急激に高分子の鎖が断ち切られ粘性の低下が始まります。
また、腐敗による蛋白質の分解が始まると1日単位で粘性が無くなり、強烈な腐敗臭を発生し作品を台なしにする危険があります。
そのため磨墨液は、磨ったその日に使いきり、使った筆、硯はきれいに洗っておくことを教えているのが“宿墨は使うな”ということなのです。
また、2~3日前に溶解した膠液で顔料を練って用いた場合は、近い将来に顔料の剥離が起こりますし、最悪の場合は作品から悪臭を発することもあります。
これ程取り扱いが難しいのが膠なのです。
このことからお解りのように、固形墨には最も適した材料である膠は、安定な液体墨を造るための材料としては、最も不安定な物なのです。
「すらずに書ける」液体墨の開発の最初は、勿論膠の二次処理から始まりました。
①ゲル化を止めること
②加水分解による粘度低下をできるだけ遅くすること
③腐敗を止めること
これが安定した液体墨を造るための条件です。当時から墨汁を造っておりましたので大体の目安をつけることはできました。
先ず、ゲル化温度の低い低重合度の膠(分子量の小さい低粘度の膠が最も安定)を探すこと。
それによりニガリ(塩化マグネシウム)の量を減らすことができ乾燥が早くなる。防腐処理を完全にする。
この開発を通じて、あらゆる膠の試験を繰り返すことにより、先代社長は膠の性質を会得し、かつ、液体墨の原料としての膠の物理的限界を感じたのかもしれません。
膨大な試作試験の結果、高濃度の練り墨状にすることにより、これまでに無い書道専用の液体墨として、“すらずに書ける”「墨の精練り墨」として発売させて戴きましたところ、法外のご好評を得て生産が追いつかず、お得意先様にご迷惑をかけながらも会社発展の大きな第一歩の開発となりました。
黒みはやや弱いものの淡墨では美しい色調が、以後の淡墨専用の「条幅用墨の精」に発展しています。
しかし、蛋白質の加水分解による粘度・分散力の低下は、薬物、機械の高度化でも自然の摂理には逆らえず限界があります。
塩分で膠のゲル化を抑えることが、より表具性を弱くし、その上加水分解による粘度低下により、煤の凝集が起こるのですから益々弱くなるのです。
ただ表現において、この蛋白質の分解の過程で芯と滲みのバランスが変化しますので、淡墨用としては面白いと思いますし表具も充分可能です。
膠を原料とした液体墨を普通の濃さ(固形分10%程度)以上の濃度で使い、表具屋さんに持ち込みますと、さすがはプロで一目で見分け、フィクサ-という合成樹脂製の固着剤をサッと吹き付け表具してくれます。
何のことは無い、この製品は固形墨と同じ天然膠で造りましたと売り込んでも、できあがった作品の上に、合成の皮膜がもう一枚乗るのです。表具屋さんで吹き付けてくれる合成樹脂の皮膜が、余白の部分まで飛び散り、時間経過と共に変色する紙に、曼陀羅模様が出るのではないかと心配しています。
表具屋さんにどうして見分けるのかを聞きますと、“寝ている墨は危ない”、“起きている墨は大丈夫”と禅問答のような返事です。よくよく聞ききますと、紙が縮んで入れば大丈夫、縮んでいなければ危ないと解り納得しました。
先代社長は、練り墨はを開発する過程で徹底的に膠を研究し、液体墨の原料としての膠の物理的限界を感じたのでしょう。
ここに全く膠を使わない、新しい液体墨を造ろう。それはゲル化のない、加水分解もない、腐敗しない、そして表具のできる学童に使いやすい液体墨でなければならない。これが合成糊剤を原料とする液体墨の開発の始まりとなったのです。
手慣れた膠を使わないのですから、何から手をつけていいか皆目解りませんでした。
これまでの墨屋のカンだけでは手も足も出ないと考えた先代社長は、当時工業試験場の場長を務めていた兄に相談し、技術者を採用して開発を始めたのです。その頃は高分子科学もまだまだで、それほど種類も無かったと思います。
昭和33年頃にはポリアクリル酸ソ-ダ-を原料として、液体墨らしい物ができ上がりました。
膠を使いませんからゲル化もありませんので、ニガリも要りません。水中でも膠と比較できないほど安定です。
合成物ですからそれ自体の腐敗もありませんし、表具性も完璧です。夢のような材料ですが、ただ一つカ-ボンとの相性が悪いのです。墨屋用に造った原料ではありませんし、膠とは丸っきり性質も違います。
これまで使っていた町の鍛冶屋の混和機程度では皆目歯が立たず、6kgのカ-ボンを処理するのに1日掛かる始末で、それでも完全な分散ではありません。
一番大きな欠点は膠製品に比べ書きにくいことです。それでも珍しいのか少しずつ売れ始めました。
担当していた技術者は墨屋の将来に見切りをつけたのかやめていきました。
当時大学生で応用化学を専攻していた現会長は、まだ教養課程で何の知識もありませんでしたが、先代社長から次々に質問が参りました。文献を調べ、高分子化学の教授に意見を聞き、訳も分からず報告したものが、社長経由で現場にいくという始末で、この時から合成樹脂を原料とした墨液の開発が現会長の仕事となりました。
爾来40年近く、その間には大失敗もありお得意先、先生方に大変ご迷惑をかけたこともありましたが、改良に改良を加え、初期の液体墨とは丸っきり違う配合となりましたが、次々に新製品を世に出すことができ、会社発展の第二の開発となりました。
書き味につきましても、固形墨と比べれば今一歩の感がありますが、膠を原料とした液体墨に比べ遜色の無いところまで参りました。